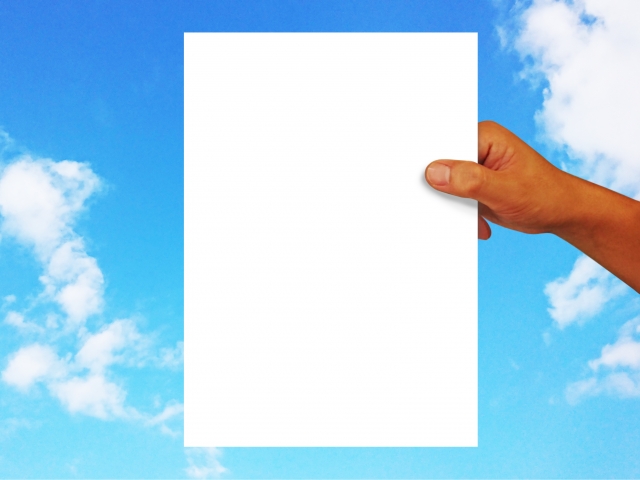はじめに
今回、東京簡易裁判所に提出した敷金返還等請求の訴状について紹介しておりませんでしたので、
その内容について記載したいと思います。
複数回に分けて記載したいと思います。第2回です。
紛争の要点(訴訟の原因)
請求の要点(訴訟の原因)には、請求を理由づける事実を具体的に記載します。
第1 敷金返還請求
まず、敷金返還請求について記載しました。
1 賃貸借契約の締結から明渡しに至るまで
賃貸借契約の締結から明渡しに至るまでの経緯について記載しています。
第1 敷金返還請求
1 賃貸借契約(転貸借契約)の締結から明渡しに至るまで
(1) 原告及び訴外■■株式会社(以下「訴外■■」という。)は、被告オーナー会社(以下「被告オーナー会社」という。)との間で、以下のイ記載の賃借物件(以下「本物件」という。)について、賃貸借契約(以下「旧賃貸借契約」という。)を締結し、引渡しを受けた。この契約の内容は、貸室賃貸借契約書(以下「契約書」という。)のとおり(甲第1号証の1)であり、契約の概要は、以下のアからオまでのとおりである。
なお、訴外■■は、原告の勤務する会社であり、現在は、株式会社■■に社名変更している。
ア 契約日 平成19年■月■日
イ 賃借物件 東京都■■
■■タワー ■■号室
ウ 貸借期間 2年
ただし、契約期間が満了する日の30日前までに、異議がないときは、契約は更新される(契約書第2条)
エ 交付した敷金の額 52万2000円
オ 敷金返還についての約定
甲(貸主)は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙(借主)及び丙(借主)に返還しなければならない(契約書第6条3項)。(2) 平成28年5月頃、被告管理会社(以下「被告管理会社」という。)からの申入れにより(甲第2号証の1)、原告及び被告オーナー会社間の旧賃貸借契約を合意解除し、新たに、原告、被告オーナー会社及び被告管理会社の三者間において、被告オーナー会社を賃貸人、被告管理会社を転貸人、原告を転借人とする、転貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
そして、被告管理会社と原告との間での賃貸借契約は、旧賃貸借契約と「同一の賃貸条件」にて締結されており、敷金返還請求権については、転貸人である被告管理会社が免責的に敷金返還債務を引き受けたことになっている(甲第2号証の2)。
なお、提出している甲第2号証の2について、下部の点線以下の「転貸借承諾書」欄に署名押印がないのは、末尾の「(注)」欄に記載のとおり、原告が署名押印したもの1通を、賃貸人である被告らに返送しており、手元に保管しているもう1通を、本訴訟の証拠として提出したためである。(3) 原告は、被告管理会社に対し、令和2年■月頃、本件契約の解約の申入れを行い、その結果、令和3年■月■日、原告は、被告管理会社に対し本物件を明け渡し、本件契約は同月■日に終了した。
なお、旧賃貸借契約及び本件契約の各終了に至るまで、原告は必要な賃料を支払っている。(4) その後、同年■月■日に、被告管理会社から、敷金52万2000円のうちの一部である11万5913円の入金のみがあったが、それ以外の金額である40万6087円が振り込まれなかった。
被告管理会社によると、この振り込まれなかった40万6087円については、本物件の原状回復工事に要する費用とのことであり、その内訳は、被告管理会社が原告に宛てて送ってきた原状回復工事見積書(甲第2号証の3)の退去者負担割合が50%及び100%の明細のとおりである。
敷金返還債務を負う被告の特定について
敷金返還義務者に対して敷金返還を請求しますが、
主位的請求、予備的請求として敷金返還請求を求める理由を記載しています。
2 敷金返還債務を負う被告の特定について
(1) 主位的請求
上記1(4)のとおり、敷金の一部しか返還してもらっていない原告は、残りの敷金返還に関するやりとりを被告管理会社と行っていたところ、被告管理会社から、「本物件の貸主は被告オーナー会社に戻ったから、敷金の返還請求権の相手方は、被告オーナー会社になる。」と電話やメールでやりとりがあった。
また、被告管理会社及び被告オーナー会社の双方から委任を受けたとする■■総合法律事務所の■■弁護士(以下「■■弁護士」という。)からも、「公社から委任された代理人として、貸主はオーナー会社」であるとの説明があった(甲第3号証の4、甲第3号証の8)。
そこで、貸主の地位が被告オーナー会社に戻ったとのことから、主位的請求として、原告は、被告オーナー会社に対し、本件契約の終了に基づく敷金返還請求として、40万6087円の支払を求める。(2) 予備的請求
もっとも、原告は、被告オーナー会社から、令和3年■月■日及び同年■月■日の電話で、「うち(被告オーナー会社)は貸主じゃないんです。」、「管理会社(被告管理会社)が貸主になってまして」(甲第8号証の1、項9と項11)、「訴訟のかたちになるとすると、管理会社(被告管理会社)を相手方でやって頂かないといけなくなる」(甲第8号証の2、項15)と明確に説明を受けた。(詳細は、後記(3)の「経緯」に記載のとおり。)また、被告管理会社の説明では、貸主たる地位が被告管理会社から被告オーナー会社に戻ったとのことだが、その際に、貸主がもとに戻ったことに関する承諾依頼書やお知らせを原告は被告らから受領していない。
よって、上記1(2)に記載のとおり、貸主たる地位が被告オーナー会社から被告管理会社に移ったが、被告オーナー会社の電話での説明のとおり、その後、貸主たる地位が被告オーナー会社に戻っていない(上記2(1)のとおりになっていない)可能性を排除できない。
被告管理会社の主張(貸主たる地位は被告オーナー会社)と、被告オーナー会社の主張(貸主たる地位は被告管理会社)のいずれが正しいのかは明白ではないが、被告管理会社または被告オーナー会社のいずれかが貸主たる地位を有していることは明白である。
そこで、予備的請求として、原告は、被告管理会社に対し、本件契約の終了に基づく敷金返還請求として、40万6087円の支払を求める。(3) 経緯
上記(1)、(2)のとおり、主位的請求として被告オーナー会社に対し、予備的請求として被告管理会社に対し、敷金の返還を求めているが、その経緯の詳細は以下のとおりであり、時系列に沿って説明する。
まず、上記1(4)のとおり、本物件を明け渡し後、敷金の一部しか返還してもらっていない原告は、残りの敷金返還に関するやりとりを被告管理会社と行っていたところ、被告管理会社から、「本物件の貸主は被告オーナー会社に戻ったから、敷金の返還請求権の相手方は、被告オーナー会社になる。」と電話やメールでやりとりがあった。
そこで、原告は、被告オーナー会社に電話で問い合わせたところ、担当者の■■氏から上記2(2)のとおり、令和3年■月■日及び同年■月■日の電話で回答があり、「うち(被告オーナー会社)は貸主ではない」、「訴訟のかたちになるとすると、管理会社(被告管理会社)を相手方でやって頂かないといけなくなる」(甲第8号証の1、2)と明確に言われた。さらには、■■氏に対し、■■弁護士が原告に対し、「オーナー会社から委任を受けた弁護士」として連絡をしてきている旨を伝えたところ、■■氏は、「(■■弁護士は)私どもの法律の顧問弁護士ではないんですよ、そこの事務所。私どもは別のところに法律顧問で委託をする先がありますんで。」、「まだ現状は委任をするかたちにはなっていません。」(甲第8号証の2、項13と項27)との返事があった。
その後、■■弁護士から、「本物件の貸主(賃貸人)は、通知人オーナー会社となります。」という被告公社の返答と相いれない回答が書面であった(甲第3号証の4)。
以上のとおり、これまでの被告ら及び■■弁護士とのやりとりからもわかるように、被告ら及び■■弁護士の三者で言っていることの整合性がとれず、そのため、その三者できちんとした意思疎通が図れているのかに不安を覚えた原告としては、被告オーナー会社と被告管理会社のどちらを本来の請求の相手方とするべきか確証がもてないことから、本来の対象でない者に対して訴訟を提起して空振りに終わる事態を避けるために、主位的請求、予備的請求として、敷金返還請求を求めるものである。
第3回へ続きます。